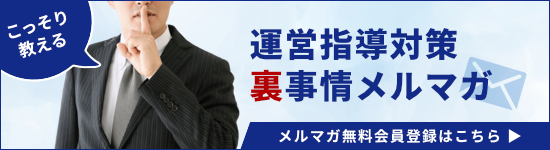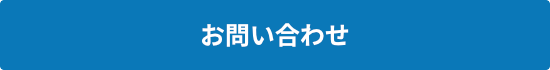- ホーム
- 講演・メディア・お知らせ
- 介護ビジョン5月号掲載 介護関連の有効求人倍率急騰による人材確保の影響と対策
介護ビジョン5月号掲載 介護関連の有効求人倍率急騰による人材確保の影響と対策
2020/04/20有効求人倍率は、会社にとって低い方が嬉しいです。
例えば、以下の図(平成31年4月)の「大阪府」を見てみましょう。介護分野の有効求人倍率が4.94倍となっています。これは、4.94社が1人求職者を奪い合う倍率であることを意味します。
参考までに、介護関連の有効求人倍率は5年前(平成24年2月)約1.88倍から約3倍上がっているとのことです。
反対に、求職者にとっては、4.94社の事業所から選べるというメリットが求人倍率です。次の図の左では、日本全体の有効求人倍率が平成22年以降ずっと上がり続けています。これは「人口減」を原因とする不可避の未曾有の社会問題「人手不足」だからです。その傾向はどんどん広がるばかりです。逆に下がり続けているのが「失業率」。最近、「面接に遅刻する」「採用なのに連絡がこない」等、嘆いていても始まりません。求職者にとっては「仕事余り」の新しい時代に入ったのですから。失業率が下がることは日本社会にとってはいいことかもしれませんが、経営者にとっては大変です。求人者がどんな能力でも、礼儀がダメでも、採用して活かすこと。かっこよく言うと「ダイバシティ推進」が経営者の手腕であり、事業所の継続と発展につながらないと言うことです。
人材確保の対策
最近、介護事業での採用で「大きい企業に入りたい」と言う求職者よりも「小さくてもやりがいのある企業に入りたい」が増えています。しかし、小さいところほど、人事評価や研修制度、昇進や昇給スシテムが整っていないことが多く、属人的な指導で、その事業所でしか通用しない人材育成でしかなく、私から職員育成マニュアルを提案しても「うちみたいな小さいとこにはまだ不要」で片付けられることもあります。結局、大手に入り直す方が教育研修や昇格や給与の将来像を描きやすいと言うスパイラルになってしまうことが一番残念です。そうならないために小中堅事業には、新しい特定処遇改善加算の導入と活用からでも遅くないので、今までの考え方を大きく変えて新しい価値観を創り出して頑張ってもらいたいです。
1) 企業理念の再確認
我々は社会福祉の仕事をしている以上、高齢者、障害者、母子家庭、LGBT、災害弱者、前科者、AYA世代重病者等を活用するソーシャルインクルージョンの取り組みは他業界以上に重要です。
2)地域の競合事業所との情報交換と人事交流
災害的人手不足の時代に「介護人材」の地域の競合社と取り合いしている場合ではありません。せっかくの介護人材を地域でどう活用するか今こそ連携していく必要があるはずです。
3) 副業・兼業の採用
介護業界以外からの採用も着手していきたいものです。ただし、もらうばかりではなく、自社の大切な人材にもそれを承認し他社へ提供する経営者の度量の大きさも大事になるでしょう。
4) 超短時間のワークシェアリング
「1日3時間、週3回上」と言う求人もだいぶん少なくなってきました。しかし、これからは「1日30分、月1回程度以上」「送迎1人」「入浴援助1人」でも可能と言う働き方にも準備していく必要があります。
-
 CareTEX大阪西村栄一講演動画「BCP、LIFE新しい運営指導の荒波をどう乗り越えるか」セミナー配信。
開催 2023年3月20日~2023年6月19日。実施場所 CareTEX365オンラインホームページ。聴講無
CareTEX大阪西村栄一講演動画「BCP、LIFE新しい運営指導の荒波をどう乗り越えるか」セミナー配信。
開催 2023年3月20日~2023年6月19日。実施場所 CareTEX365オンラインホームページ。聴講無
-
 介護事業者連盟全国大会2024の開催
全国介護事業者連盟全国大会in東京2024の開催が近づいてきました!定員3000人11月6日(水)10時〜18
介護事業者連盟全国大会2024の開催
全国介護事業者連盟全国大会in東京2024の開催が近づいてきました!定員3000人11月6日(水)10時〜18
-
 通所ケア研究会の開催!もちろん私も11/1の夕方!サンセットプレセミナーでしゃべります!
自信を持って取り組む運営指導対策【講師インタビュー:西村 栄一 氏(株式会社ヘルプズ&カンパニー)】https
通所ケア研究会の開催!もちろん私も11/1の夕方!サンセットプレセミナーでしゃべります!
自信を持って取り組む運営指導対策【講師インタビュー:西村 栄一 氏(株式会社ヘルプズ&カンパニー)】https
-
 当社直営3号館目のグループホーム(障害支援包括型)、ショートステイ開業!
シェアハウスりぼん3号館のご案内。来年の万博会場のターミナル弁天町駅のショッピングモールオーク200から徒歩5
当社直営3号館目のグループホーム(障害支援包括型)、ショートステイ開業!
シェアハウスりぼん3号館のご案内。来年の万博会場のターミナル弁天町駅のショッピングモールオーク200から徒歩5
-
 2025.3.25 西村栄一ニューヨーク公演
既報通り3月末、JAA様主催の「日本の介護事情セミナー」をさせていただきました。思い立ったのは3月上旬。「そう
2025.3.25 西村栄一ニューヨーク公演
既報通り3月末、JAA様主催の「日本の介護事情セミナー」をさせていただきました。思い立ったのは3月上旬。「そう