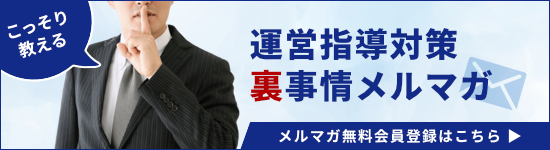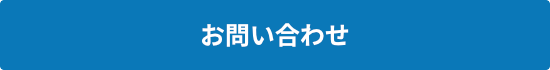- ホーム
- 西村栄一のブログ
西村栄一のブログ
問われる介護先進国日本

アメリカもそうだと思いますが、ワールドベースボールクラッシック盛り上がってますねえ。日本の圧倒的強さが光るこの大会(3/11時点)。いつも「奇跡」とか「下剋上」というワードで2歩も3歩も引いて挑むことが多いここ最近の日本のあらゆる場面で、この「圧倒的」な強さは春のポカポカ感と咲き始めたサクラと「脱マスク」で開放感に浸って清々しいことこの上ありません。という現在の心境です。
そんなスポーツというと「強さ、速さ、技」の優劣が勝敗を分けると思う人も多いかもしれませんが、スポーツにはそれ以上の「知能と準備」がそれらを上回るのです。(参考:大谷翔平マンダラチャートより)それは介護のプロの世界でも同じです(勝敗を分ける競技ではありませんが)。介護は、優しさと奉仕の心で成り立っていると思われがちですが、「インテーク」や「アセスメント」にその方の要介護の前までの人生、生き様や経験を理解するナラティブという準備とそれを生かす知能を重視する向きもあります。一番いけない介護が、目の前で起きていることだけ解決する対処法と技術だけによる自己満介護です。よく言われる美辞麗句が「私は利用者様の笑顔・ありがとうの言葉が仕事のやりがいなんです」という一見綺麗に見えるが、全くのNGワード。毎日「ありがとうを言わされる利用者」は笑顔と感謝がないとやる気にならない職員へ気を使いすぎてしまうある種の「犠牲者」でもあると私は思います。そんな捻じ曲がったやりがいしか持てない職員はとっとと出て行ってもらってもいいでしょう。正しい介護は利用者に気づかれないように事前に察して、自然に気持ち良くさせることです。そのための「知能と準備」であり、それがあって初めて「合理性」が加わるというものです。新人や見習いの時は「若いくせに合理性を重視するな」とか「無駄という非合理性がその人の伸び代を強化する」等、合理性を否定されて日本人は生きてきたはずです。確かに「合理性だけで生きていると予測できない非常時の対応ができない」と言われることも当然だと思います。
特に、介護は生産的な活動だとは思われていません。介護の必要な方をこの世からなくして、発展性のあるものやことへの投資&労働集約する方が国土発展に寄与することが一番の合理性なのかもしれません。しかし、そういう学者がいて、賞賛されることには私は大きな違和感を感じます。認知症の方のとりとめもない話を何時間でも聞くこと、衰えいく方の生活に潤いを与える時間を提供すること。その方のなんでもない日常に、プロの知能を生かしたナラティブと準備に時間をかけること。一見非生産的に見えるこの業務こそ「合理的な活動」と言わず、何が合理的なのでしょうか。それを削ぎ落としてやる介護は一方通行の自己満足介護でしかありません。
しかし、そうはいっても、OECD加盟国の中での日本は「労働生産性」という視点で、就業1時間当たり付加価値は、49.9ドル(5,006円)。 OECD加盟38カ国中27位とのこと。対する米国は85.0ドル(8,534円)。(参考:公益財団法人日本生産性本部2022より)
人口減少下での日本での労働力に無駄をこれ以上は生むわけにはいきません。さらに、そうでなくても非合理と言われる介護労働者のそれが行き過ぎると、少人数の介護労働者の時間の拘束による「過剰労働」に直結する可能性もあることも事実です。今一度、「介護の合理的とは?」と見直しも必要とは感じています。介護の非合理性を日本の文化と早合点して改善することをしないままでは「世界の介護サービス先進国日本」としての信用も高まらないでしょう。その視点をぶらさずに「新しい合理的な日本の介護」をAIやデジタル技術を通して発見していくことが事業所には求められていくと私は確信しています。(週刊NY生活905号 2023/3/18より抜粋)
#運営指導 #旧実地指導 #介護保険実地指導 #介護保険運営指導 #実地指導対策 #運営指導対策 #介護事業所指導監査 #介護施設監査対策 #行政指導対策 #介護保険指導監督 #デイサービス実地指導 #訪問介護実地指導 #通所介護運営指導 #通所リハ実地指導 #介護施設運営指導 #介護施設運営適正化 #介護コンプライアンス #介護法令遵守 #介護加算算定チェック #介護記録指導 #介護運営コンサルタント #介護運営コンサル #介護経営コンサルタント #介護事業経営コンサル #介護事業所コンサル #介護施設コンサルタント #デイサービス経営コンサル #訪問介護経営コンサル #介護保険施設コンサル #介護事業立て直し #介護事業所改善 #介護事業所運営改善 #介護事業所経営改善 #介護経営安定化 #介護BCP支援 #科学的介護LIFE #LIFE対応支援 #介護業務改善 #介護現場改善 #介護労務リスク #西村栄一 #ヘルプズアンドカンパニー #ヘルプズアンドカンパニー西村栄一 #実地指導レスキュー #運営適正化レスキュー #日本で唯一の介護事業所の運営適正化レスキューコンサルタント #介護運営指導の専門家 #実地指導一筋 #実地指導対策のプロ #運営指導の達人 #介護事業コンプライアンス講師 #介護経営セミナー講師 #介護保険指導監督研修講師 #実地指導準備 #実地指導シミュレーション #模擬実地指導 #運営指導事前対策 #運営指導チェック #実地指導書類整理 #介護記録整備 #個別支援計画指導 #ケアプラン点検 #加算要件確認 #返還金リスク対策 #指導監査で指摘されないために #実地指導で慌てない #訪問介護計画書指導 #デイサービス運営見直し #生活相談員体制整備 #人員基準の見直し #運営規程整備 #指導後改善フォロー #介護事業者向けコンサル #介護施設経営者向け #訪問介護事業者向け #デイサービス事業者向け #居宅サービス事業者向け #大阪介護コンサル #関西介護コンサル #全国対応介護コンサル #介護経営者のお悩み解決 #介護事業所の不安解消 #介護事業者支援 #介護事業のよろず相談 #介護経営なんでも相談 #介護事業所の駆け込み寺 #現場重視の介護コンサル #机上の空論ゼロ #介護ヘルパーは日本で一番魅力のある仕事 #企業は人なり #介護経営と現場の両立 #介護事業の持続可能性 #利用者の幸せと経営の両立 #介護業界を良くしたい #介護事業所の未来を守る
超・生産性向上への挑戦

ただ、介護のお仕事に売上アップとか、効率化という言葉は違和感があるのも間違いありません。売上アップするためには利用する本人が不要なサービスや過剰ともいえるサービスを提供する悪質な方法をする事業所も出てくるかもしれないし、効率化というと、温かみのない割り切ったドライな関係でないといけないかもしれないですよね。ただし、経営者としては、職員が給与をもらっている以上、生産性を上げる、時間当たりの売上単価というものは無視するわけにもいきません。介護や福祉には、そもそも売上や効率化は相応しくないと言い切ってしまえば元も子もない。それは、せっかく介護制度を育成してきた実績を否定することであり、ミレニアム(2000年)以前の「お上(自治体等)からいただく、選ぶ権利のない措置制度に立ち返ってしまうということがいいはずもありません。
そんな中、当社障害者グループホームでは「超・生産性向上」を掲げることにしましました。
簡単にいうと、「サービスを受けている方(利用者)にも働いてもらうことはできないか?」という策です。もちろん、障害者を雇用するということは何も珍しいことではありませんし、公的制度としても、就労移行支援、就労継続支援、自立訓練、社会生活適応訓練と類似の制度活用方法はいくつかあります。そこがどう違うのか、さらにわかりやすく、飲食で例えるなら、「牛丼を食べにきた人が、そのまま、厨房に片付け、皿洗いしてもらう」または、「お客さんとして来店しているのに、マスターがヨボヨボで放っておけないので、カウンターの中に入り、次に来店したお客さんのオーダーを聞いてマスターの代わりにサービス提供する」ようなものですかね。しかも、それを「勤労と認め時給を払う」という、「消費しながら生産する」という方法です。
このことを大阪市指導課に確認したところ、「他の利用者の混乱を招かないように利用する側とサービス提供する側の時間・場所等の区分けができれば可能」という判断をいただきました。
実は、その類似例として、学生向けマンションや宿舎を提供する条件として「月●時間のボランティアや地域活動に参加する義務を付与して入居させる」というものもあります。
例1:シェア金沢ミッドタウン(石川県金沢市若松町)の学生向け住宅。
例2:ワテラススチューデントハウス(東京都千代田区)
ただし、事例として挙げた2例は「給与代わりの現物支給」でもあり、その点では当社は「給与を支給する」点では、独自の「超・生産性向上への挑戦」だと自負しています。
日本の産業全体が人手不足になりつつある中、これらの問題は、AIや外国人に頼るにはまだハードルが高すぎます。しかも、その進化や制度の緩和を待っているわけにはいかないのです。そこにはお客様が待っているのですから!(週刊NY生活プレス2023/3/4 903号より抜粋)
#運営指導 #旧実地指導 #介護保険実地指導 #介護保険運営指導 #実地指導対策 #運営指導対策 #介護事業所指導監査 #介護施設監査対策 #行政指導対策 #介護保険指導監督 #デイサービス実地指導 #訪問介護実地指導 #通所介護運営指導 #通所リハ実地指導 #介護施設運営指導 #介護施設運営適正化 #介護コンプライアンス #介護法令遵守 #介護加算算定チェック #介護記録指導 #介護運営コンサルタント #介護運営コンサル #介護経営コンサルタント #介護事業経営コンサル #介護事業所コンサル #介護施設コンサルタント #デイサービス経営コンサル #訪問介護経営コンサル #介護保険施設コンサル #介護事業立て直し #介護事業所改善 #介護事業所運営改善 #介護事業所経営改善 #介護経営安定化 #介護BCP支援 #科学的介護LIFE #LIFE対応支援 #介護業務改善 #介護現場改善 #介護労務リスク #西村栄一 #ヘルプズアンドカンパニー #ヘルプズアンドカンパニー西村栄一 #実地指導レスキュー #運営適正化レスキュー #日本で唯一の介護事業所の運営適正化レスキューコンサルタント #介護運営指導の専門家 #実地指導一筋 #実地指導対策のプロ #運営指導の達人 #介護事業コンプライアンス講師 #介護経営セミナー講師 #介護保険指導監督研修講師 #実地指導準備 #実地指導シミュレーション #模擬実地指導 #運営指導事前対策 #運営指導チェック #実地指導書類整理 #介護記録整備 #個別支援計画指導 #ケアプラン点検 #加算要件確認 #返還金リスク対策 #指導監査で指摘されないために #実地指導で慌てない #訪問介護計画書指導 #デイサービス運営見直し #生活相談員体制整備 #人員基準の見直し #運営規程整備 #指導後改善フォロー #介護事業者向けコンサル #介護施設経営者向け #訪問介護事業者向け #デイサービス事業者向け #居宅サービス事業者向け #大阪介護コンサル #関西介護コンサル #全国対応介護コンサル #介護経営者のお悩み解決 #介護事業所の不安解消 #介護事業者支援 #介護事業のよろず相談 #介護経営なんでも相談 #介護事業所の駆け込み寺 #現場重視の介護コンサル #机上の空論ゼロ #介護ヘルパーは日本で一番魅力のある仕事 #企業は人なり #介護経営と現場の両立 #介護事業の持続可能性 #利用者の幸せと経営の両立 #介護業界を良くしたい #介護事業所の未来を守る
緊急時の対応について思うこと

大雪、大雨。ちょとした気候の変化でも日本列島大騒ぎしてしまうもんです。毎年この時期は。で、そのたびに感じる日本人の民度、民族性があります。介護、福祉は、他産業よりも「人と人」の色合いがどうしても濃いので、表面だけはデジタル革命ができても、人の心の底辺を流れる民度が変わらないと働きの根元の「革命」は起こらないと思います。
例えば、先日「十年に一度の最強寒波」到来についても、近づいてくる天気図を眺めながら日本全国が文字通り震え上がっていました。そんな中で、起きるべくして起きた「交通機関の麻痺」。特に「電車に10時間閉じ込められた7千人」という話は、当事者意識としてもゾッとする出来事でした。もし、私にそれが起きた場合、たぶん「開けろー」「トイレいきたい、いけないならここでするー」と発狂していただろうという想像と感想。しかし、主要ニュースやツイッターを覗き込んだところ、私の感想は意外とほとんどない様子。主には、「会社側は乗客に謝罪する必要はない」「寒波が来るとわかっていても乗車した乗客の自己責任」「いかなる状況でも外に出したり、線路を歩かせる判断は危険」「外より中の方が安全」が大多数で、私と類似の意見「会社側の危機管理の甘さ」「対応や判断の迅速ではない」は少ないのです。私は思いました。
何年たっても変わらない「団体行動優先で自己犠牲をもいとわない一億総◯◯社会」だなあと悔しくなりました。だから、介護の「自立支援」でさえ、虚しくなるほど「自立することが団体からはみ出る恥」とさえ価値づけられているのかなと短絡的ですが思ってしまうのでした。
さて、コロナ禍のような災害時や感染症が広がっていても、休まずに働き続ける人たちのことを「エッセンシャルワーカー」という「命の番人」がいることが注目されました。エッセンシャルワーカーの定義は「人々が社会生活を営む上で欠かせない、生活インフラや社会 インフラを維持する仕事に従事している人々」といいます。もちろん、ここでいう電車会社もそのひとつです。人や物の移動(輸送)、倉庫、介護・医療、小売、公務、農業から10業種が選ばれています。それらは「国民の大多数が困難になればなるほどに必要な労働力」でありながら、その特性上、その仕事のせいでその災害や感染等の犠牲にもさらされている(野城尚代2021東洋大学)」といいます。今回の大雪という災害禍の人の移動においても電車会社は、そのプロ意識があまりにも低すぎたのではないかという非難はもっとあるべきだし、そのプライドでさえなかったと思っています。
我々介護関係者は、この半年、そして、来年2024年3月末を目処に、「いつ何時でも災害や感染症、またはそれ以外のテロやストライキ、インフラの急な停止による事件事故でも、事業が継続でき、止まっても至急に復旧できるための計画書の策定に追われています。そんな最中のことに対して、国民が甘くしていては、近い将来もっと大変なことが来るという「一億総倒れ」にならないような国づくりをしていかなければならないと思います。幸いにもその電車会社は、翌日記者会見で、社長自らが猛省されました。このことが日本の民族性の危機管理とその予防と復旧と対応と判断の目安のきっかけになればと思います。そして、そろそろまたやってくるあの東日本大震災から12年。改めて、岩手県の災害時の標語「つなみてんでんこ」が、ぼーっと生きている自分に対しての「正常性のバイアス」を排除するような警鐘を感じる出来事だったのでした。(週刊NY生活プレス2023年2月11日900号より抜粋)
#運営指導 #旧実地指導 #介護保険実地指導 #介護保険運営指導 #実地指導対策 #運営指導対策 #介護事業所指導監査 #介護施設監査対策 #行政指導対策 #介護保険指導監督 #デイサービス実地指導 #訪問介護実地指導 #通所介護運営指導 #通所リハ実地指導 #介護施設運営指導 #介護施設運営適正化 #介護コンプライアンス #介護法令遵守 #介護加算算定チェック #介護記録指導 #介護運営コンサルタント #介護運営コンサル #介護経営コンサルタント #介護事業経営コンサル #介護事業所コンサル #介護施設コンサルタント #デイサービス経営コンサル #訪問介護経営コンサル #介護保険施設コンサル #介護事業立て直し #介護事業所改善 #介護事業所運営改善 #介護事業所経営改善 #介護経営安定化 #介護BCP支援 #科学的介護LIFE #LIFE対応支援 #介護業務改善 #介護現場改善 #介護労務リスク #西村栄一 #ヘルプズアンドカンパニー #ヘルプズアンドカンパニー西村栄一 #実地指導レスキュー #運営適正化レスキュー #日本で唯一の介護事業所の運営適正化レスキューコンサルタント #介護運営指導の専門家 #実地指導一筋 #実地指導対策のプロ #運営指導の達人 #介護事業コンプライアンス講師 #介護経営セミナー講師 #介護保険指導監督研修講師 #実地指導準備 #実地指導シミュレーション #模擬実地指導 #運営指導事前対策 #運営指導チェック #実地指導書類整理 #介護記録整備 #個別支援計画指導 #ケアプラン点検 #加算要件確認 #返還金リスク対策 #指導監査で指摘されないために #実地指導で慌てない #訪問介護計画書指導 #デイサービス運営見直し #生活相談員体制整備 #人員基準の見直し #運営規程整備 #指導後改善フォロー #介護事業者向けコンサル #介護施設経営者向け #訪問介護事業者向け #デイサービス事業者向け #居宅サービス事業者向け #大阪介護コンサル #関西介護コンサル #全国対応介護コンサル #介護経営者のお悩み解決 #介護事業所の不安解消 #介護事業者支援 #介護事業のよろず相談 #介護経営なんでも相談 #介護事業所の駆け込み寺 #現場重視の介護コンサル #机上の空論ゼロ #介護ヘルパーは日本で一番魅力のある仕事 #企業は人なり #介護経営と現場の両立 #介護事業の持続可能性 #利用者の幸せと経営の両立 #介護業界を良くしたい #介護事業所の未来を守る
介護の敷居が高くなる?

2023年の日本の介護は翌年2024年の介護・診療・障害者の制度と報酬の同時改定の議論が丸一年かけて年末までにまとめられる重要な年になります。
ちょうど我々50代60代の「まだ介護のお世話になはならないのよ」という壁ぎわ世代がこの先25年の介護のあり方の「原点年」にもなるので、いつもよりも介護のニュースには自分事として気をつけておきたいです。特に以下の点にご注目ください。
1 これまで貰えていたはずの介護保険対象の水準が上がってしまう
2 これまで払わなくてもよかった介護保険負担額が上がってしまう
3 マイナンバー制度の本格化で医療介護栄養運動薬等の健康情報がデータ一元化(科学化)
4 これまで認められていなかった介護の新サービスが生まれる
介護保険制度は今年23歳になります。かつては「家族以外の他人に家に入られて親の面倒みられるなんて恥」という固定観念がなくなりつつあり(田舎に行けばまだ残っていますが)、都会では「介護は国民の権利」「せっかく国からもらえるサービスはどんどん受けなきゃ損」ということで、「できないことのお世話」「お世話に疲れ切った家族の休暇の時間」という常識に成長してきました。ということで、2023年からは介護を受けられる敷居が高くなり、医療依存度の高い「重度者」や、介護の面倒みる人が周囲にいないなどの「生活困窮者層」と極端に分けられ、これまでの「介護を受けたい」中間所得層や「まだ動ける」中途半端に元気な層が「介護が受けられない」と路頭に迷ってしまう時代がきます。ある意味、その敷居が高くなることはかつて介護制度がなかった時代(2000年以前)に逆行していると言っても過言ではないと言えます。これは困ったものです。ただし、同時に日本は先進国ではまれでもある「人口減少国家」でもあるため、他国以上にいわゆる「AI導入」が急がれています。遅れていた「マイナンバー制度」もやっと定着してくるでしょう。それによって介護・医療・栄養・運動・薬等の健康情報のデータ一元管理され、介護を受けたい中間層が路頭に迷わないようにさまざまな書類や情報へ応用され、「元気高齢者」をたくさん育てる方向に日本は指針を示しています。そんな中で、同じく路頭に迷いそうなデイサービスも新しい「介護新サービス」として、新しい社会資源として役割を与えられることでしょう。かつてのデイサービスのイメージが一新されつつあります。国の指針とは以下の通りです。
1 訪問介護とデイサービスを連続して使える複合型サービス
2 お仕事感覚でバイトできる(お金稼ぐことができる)デイサービス
3 短時間で「午前中だけ」や「午後だけ」と試食感覚の体験型デイサービス
4 スタッフが法人という垣根を取っ払ってUberEats並みに自由に行き来できるデイサービス
つまり、この23年でイメージがついた「介護を受ける権利」という時代から「介護Re-born」へ。まだサービスを提供している側である我々50代60代がリアルに高齢者になるこの10年20年でエンタメ要素の強い介護サービスが国の指針とともに生まれることに期待したいです。国は、そのきっかけとして、事業所の報酬ツールとして「排泄支援加算」「自立支援加算」等の要介護者個人の尊厳を重視したハードルの高い報酬ツールも設定してくれています。その期待に事業所側はなかなか難しいのですが、それに挑戦する事業所がどんどん出てくることに期待したいと思います。
国と事業所、国と我々50代60代、国と要介護者、それと周辺の関係各位医療、栄養、運動、薬。どれも悠長な時間はありません。気を抜かず2023年をスタートさせたいと思います。今年の一文字はreborn。「再生」の「再」で行きましょう!やり直しのできる世の中って素敵ですよね!(週刊NY生活2023年1月1日895号)
実名報道に思うこと「社会的制裁」優先に疑問
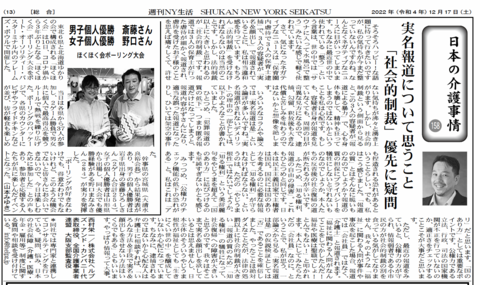
ハッピー!な話題に持って行きたいのですが、私の気持ちが今整っていないんですかね。なんとなくネガティブなニュースに目がいってしまいます。ちなみに最近世の中で使われている「整う」というのは、世の中では「サウナに入って水風呂で整う」みたいな感じで軽く使われています。
さて、ネガティブなニュース一発目は「保育園内虐待で3名の保育士逮捕」で3名の容疑者が「実名&顔出し」で報道されていることに、私は相当違和感を持っています。もちろん、「法的制裁」は受けなければならないのは当然のことです。しかし、法的制裁以上に大きいと思われるのが「社会的制裁」です。毎日の報道では、3名の保育士が行った虐待を細かく報道され、虐待を受けたお子様のことを思えば痛々しくて、許せない気持ちは沸々と湧き上がります。しかし、射愛的制裁という側面から見ると、この3名の容疑者が「報道による暴力」で、心も身体も壊して、精神もに狂ってしまうのではないかということも、私は心配です。もしも、容疑者自身が報道をみていなくても、周囲の目が奇異な見方になるので、逮捕、勾留、釈放後も大きな代償と苦しみを味わうのではないかと想像を絶します。
いろいろなコラムや論文では「実名報道は是」という論評が多いんですね。もし、「実名報道がされないデメリット」の理由の一部としては、以下のようなことが書かれていました。
ひとつめ、「犯罪報道の質の低下」。つまり、匿名報道だけになってしまうと、報道内容がずさんなり、適当な誤った報道になったりし、ひいては架空の事件も捏造される恐れがあるということらしい。でも、私はこう感じました。「報道の質」とはそんなに脆いものなのでしょうか?報道の質の担保にプライバシーを犠牲にしないと守れないものなのでしょうか。本人たちの反省後の社会復帰の道が断たれる方が辛いです。
ふたつめ、「知る権利、報道の自由の侵害」。これもひとつめと同じです。いくら日本は民主主義国家で主権者は国民。国民には国のあり方を考えるのに必要な情報として「知る権利」が守らなければならない。というのは、ただの「やじうま根性」ではないでしょうか。「知る権利」という美辞麗句をやじうまを超えて「国のあり方」に結びつけるのも単純すぎないかとも感じます。
みっつめ、「公権力のチェック機能の低下の恐れがある」と。私はこれは「アリ」だと思います。「国のあり方」としては重要なポイントです。公権力である立法、行政、司法の国家機関が不正を行っていないのか、適正さをチェックすることこそが大事だと思います。
ただし、最近の報道をみていると、公権力の方が守られ、情報弱者である小市民の方が社会的制裁の割を食っている気がしてなりません。我々のような「福祉」に関わる人間が事件や事故を起こした場合、報道では「会社員」ではなく、「介護士」と報道されます。「福祉に関わる人間がなんてことをしでかしたんだ!福祉や医療は聖職でしょ!とんでもない!」と叩かれます。本人にしてみたらただの「会社員」なのに。ということで、私が思う、一部論文から見る「実名報道は是」の仮説検証としては「否」であることを確信しました。やったことは絶対ダメなことだが、法律の処罰以上に社会的制裁が大きい「報道の質のため」「知る権利」の犠牲になって、社会復帰への障害が大きいと思うのです。我々はそこまで実名&顔出しを欲しているとは思えませんし、日本全体のそういうやじうま根性が福祉としても「生きにくい世の中」を醸成していないか心配になっています。ちなみに、逮捕されるのではないかと心配な人は弁護士に相談すれば、「いろんな方法&手段で実名&顔出しをさせない方法はいくらでもある」ともいいます。やっぱり情報って大事。(週刊NY生活894号 2022年12月17日コラムより抜粋)
#運営指導 #旧実地指導 #介護保険実地指導 #介護保険運営指導 #実地指導対策 #運営指導対策 #介護事業所指導監査 #介護施設監査対策 #行政指導対策 #介護保険指導監督 #デイサービス実地指導 #訪問介護実地指導 #通所介護運営指導 #通所リハ実地指導 #介護施設運営指導 #介護施設運営適正化 #介護コンプライアンス #介護法令遵守 #介護加算算定チェック #介護記録指導 #介護運営コンサルタント #介護運営コンサル #介護経営コンサルタント #介護事業経営コンサル #介護事業所コンサル #介護施設コンサルタント #デイサービス経営コンサル #訪問介護経営コンサル #介護保険施設コンサル #介護事業立て直し #介護事業所改善 #介護事業所運営改善 #介護事業所経営改善 #介護経営安定化 #介護BCP支援 #科学的介護LIFE #LIFE対応支援 #介護業務改善 #介護現場改善 #介護労務リスク #西村栄一 #ヘルプズアンドカンパニー #ヘルプズアンドカンパニー西村栄一 #実地指導レスキュー #運営適正化レスキュー #日本で唯一の介護事業所の運営適正化レスキューコンサルタント #介護運営指導の専門家 #実地指導一筋 #実地指導対策のプロ #運営指導の達人 #介護事業コンプライアンス講師 #介護経営セミナー講師 #介護保険指導監督研修講師 #実地指導準備 #実地指導シミュレーション #模擬実地指導 #運営指導事前対策 #運営指導チェック #実地指導書類整理 #介護記録整備 #個別支援計画指導 #ケアプラン点検 #加算要件確認 #返還金リスク対策 #指導監査で指摘されないために #実地指導で慌てない #訪問介護計画書指導 #デイサービス運営見直し #生活相談員体制整備 #人員基準の見直し #運営規程整備 #指導後改善フォロー #介護事業者向けコンサル #介護施設経営者向け #訪問介護事業者向け #デイサービス事業者向け #居宅サービス事業者向け #大阪介護コンサル #関西介護コンサル #全国対応介護コンサル #介護経営者のお悩み解決 #介護事業所の不安解消 #介護事業者支援 #介護事業のよろず相談 #介護経営なんでも相談 #介護事業所の駆け込み寺 #現場重視の介護コンサル #机上の空論ゼロ #介護ヘルパーは日本で一番魅力のある仕事 #企業は人なり #介護経営と現場の両立 #介護事業の持続可能性 #利用者の幸せと経営の両立 #介護業界を良くしたい #介護事業所の未来を守る
介護施設と縁のある有名人やアスリート

お久しぶりに歓喜の声をあげることがありました。日本サッカーが強豪国ドイツに勝ったのです。この勝利景気がもたらした効果は、おかげさまでなかなか滞って、うまくいかなった案件や難しいお客様もご機嫌良くなる傾向があって、交渉やいいにくかったこともスムーズに進むことに日本代表に感謝です。
そして、同点を挙げた堂安選手。偶然ではありますが、当社も懇意にしていただいている訪問介護、通所介護に関わるお客様の息子様でもあるのです。ビッグマウスで一部では賛否もある同選手ですが、親御様のその事業所は小さく経営されていて、質素で、まさかあの選手の実家とは思えないほど至って普通にされています。そこをご利用されている利用者様ともお話する機会がありましたが、「リフティングっていうの?上手よねえ」「たまにああいう若い人たちがここに来てくれるとなんか私たちも頑張んなきゃって思うの」と、あんまり有名人とは思っていなさそうなところも微笑ましいところでもあります。
他にも元ソフトバンク森本学選手。かつて野村克也監督の秘蔵っ子ともよばれていた同選手は、この方自身が実際に経営されています。うちの近所なので、「お醤油貸して」といったらすぐに来てくれる距離におられます。おばあちゃんおじいちゃんの通いの場でもある通所介護と障害者支援の就労継続事業所を主にされています。実はうちの入居されている利用者さんも通っているのでが「まだ森本選手に会えてない〜」と悔しがっています。ということは、利用者にとっては、サッカーの堂安選手の方が会える確率は高そうですね。
そして、うちのコンサルティングの顧問先には「利用者」として入居してリハビリに努められている方もおられます。これは匿名にしておきますが、有名なスキーヤーの方です。世界最高齢で◯◯達成を目指しておられますが、この方もメリハリがありますね。入所されている時は徹底的にサービスを駆使して、いざ退所すると全力で自分自身の能力を最大限に発揮されているのを伺うと、自分の身体に常に聞き耳をたてて、そのバランスをプロ(他人)に頼りながら、はかっておられる点がすごいと思います。
そういう方々は「老人ホーム」を悠々自適に過ごすところではなく、自立するための社会資源としての「老人ホーム」の活用をされている点が昭和時代と大きく変わった点ではないでしょうか。2年前に放送されていた視聴率王のドラマ半沢直樹に出演されていたあの男優さんも老人ホームから出勤していたそうですからね。一歩間違えると「えーかわいそう」という印象は全くない。それがこれからの老人ホームではないでしょうか。
また、働く側のやりがいも一変しています。介護業界で働くことを「何からの罪滅ぼし」や「みそぎ」とかに使われることも多かったのは過去の話。
お笑い芸人EXITのりんたろーさんはチャラ男漫才で大ブレイクし、いま最も勢いのある方です。8年ほど非常勤勤務として通所介護事業でひととおりの介護サービスを高齢者に提供されていたそうです。ご飯も作るし、お風呂も入れるし、着替えや口腔ケアまでやっていました。高齢者の方との生活を支える立場ですから、いろいろとトラブルもあったそうですが、基本的には「介護は年上ギャルとのパーティー」と語っており、持ち前のチャラさを発揮しておられます。
あ、かくゆう私もライフセービング日本選手権(2008年)チューブボードレスキュー西日本代表でした。汗
話は戻り日本代表の堂安選手。私が関わる上で感じるのは、同選手の親御様の経営姿勢自体は、「守り」そのものと見せかけて、実は大胆に「攻め」の手綱を緩めない経営は、継がれている息子様のバランスの取れた行動につながっていると確信しています。大きな歴史を刻め!サッカー日本!(週刊NY生活2022/12/3 892号より抜粋)
気が遠くなりそうな相続放棄の苦労話
 要介護1の父の軽い介護から一転、その後の死後整理の段階に入って早1か月。日本の介護事情を私自身が肌身に染みている辛さを皆様に情報共有させていただきます。これは傍観するコンサルではなく、動くコンサルの主観でもあります。今回は「相続」の件です。兄妹二人で話し合った結果。それは「放棄」という決定をしました。「世話好き」が高じて商売の延長線上でたくさんの保証人になっていることが判明。その額と督促状はちょっとした家屋が建つほどで、その書類の量も膨大で驚愕するほどでした。身震いして、その手続きに入りました。すぐに家庭裁判所に行き、話を聞いたら「こりゃ簡単」と思い、しかも、豆知識で、できるだけ早めに父名義の金融機関口座凍結し、出入金を止める。ただし、入ってくる予定の補助金や年金は父名義から私個人へ同時に切り替える。その後は、家庭裁判所に①申述書、②父(被相続人)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本戸籍等全部事項証明書、③被相続人の住民票除票又は戸籍附票、④相続人(申述人:私)の戸籍謄本」の特に②〜④を取り寄せたら、父の在住の管轄裁判所へ郵送で送れば、2週間で審理許可されれば、「受理通知書」という名称の紙が私の自宅に届きます(これ絶対無くしてはいけないやつ)。このコピーを債権者に10月中にFAXか郵送で連絡したところ、それまでの膨大な量の督促状が、ピタッと止みました。「あっけない、これで終わり?安心」と思っていたところ、次は、ここからが相続放棄の本当のお仕事ですと法テラスで確認。実は債務は父と子だけではなく、債務が父の兄弟姉妹、その子供(私からみていとこ)まで及ぶため、債権者は督促をする権利があるというのです。父の兄弟姉妹は姉(101歳:私からみて叔母)と、その子(私からみていとこ)にまとめて4種の書類を取り寄せるための「委任状」を取ることにしました。ただし、父のことで101歳の叔母にもいとこにもご足労や手間、戸籍を取る手数料等をかけさせることは最小限にしたいために家庭裁判所に再び行ってみました。そこでショックなことが起きました。父が戦中生まれだったこともあり、私にはいとこが総勢20人以上すべてに該当することが判明したのです。しかも、4種の書類に加え、さらにもう2−3種類がいるとのこと。いとこの戸籍と、既に亡くなっている親であればその親が戸籍除票、その上の親(わたしからみて祖母)の除票まで要るという手間と書類作成の量。しかも、この件をいとこらに通知依頼した瞬間から3か月以内に手続き完了させなければ特別な理由がない限り債務が継続するという早急性もあり、泣きそうになって司法書士にすがると「しかたないですね。1件4万円でどうですか?」とのこと。もう!80万かかるくらいなら全部自分でするわい!(←今ここ)このコラムをご覧いただいている司法書士の方、これであっています?(週刊NY生活プレス2022.11から抜粋)
要介護1の父の軽い介護から一転、その後の死後整理の段階に入って早1か月。日本の介護事情を私自身が肌身に染みている辛さを皆様に情報共有させていただきます。これは傍観するコンサルではなく、動くコンサルの主観でもあります。今回は「相続」の件です。兄妹二人で話し合った結果。それは「放棄」という決定をしました。「世話好き」が高じて商売の延長線上でたくさんの保証人になっていることが判明。その額と督促状はちょっとした家屋が建つほどで、その書類の量も膨大で驚愕するほどでした。身震いして、その手続きに入りました。すぐに家庭裁判所に行き、話を聞いたら「こりゃ簡単」と思い、しかも、豆知識で、できるだけ早めに父名義の金融機関口座凍結し、出入金を止める。ただし、入ってくる予定の補助金や年金は父名義から私個人へ同時に切り替える。その後は、家庭裁判所に①申述書、②父(被相続人)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本戸籍等全部事項証明書、③被相続人の住民票除票又は戸籍附票、④相続人(申述人:私)の戸籍謄本」の特に②〜④を取り寄せたら、父の在住の管轄裁判所へ郵送で送れば、2週間で審理許可されれば、「受理通知書」という名称の紙が私の自宅に届きます(これ絶対無くしてはいけないやつ)。このコピーを債権者に10月中にFAXか郵送で連絡したところ、それまでの膨大な量の督促状が、ピタッと止みました。「あっけない、これで終わり?安心」と思っていたところ、次は、ここからが相続放棄の本当のお仕事ですと法テラスで確認。実は債務は父と子だけではなく、債務が父の兄弟姉妹、その子供(私からみていとこ)まで及ぶため、債権者は督促をする権利があるというのです。父の兄弟姉妹は姉(101歳:私からみて叔母)と、その子(私からみていとこ)にまとめて4種の書類を取り寄せるための「委任状」を取ることにしました。ただし、父のことで101歳の叔母にもいとこにもご足労や手間、戸籍を取る手数料等をかけさせることは最小限にしたいために家庭裁判所に再び行ってみました。そこでショックなことが起きました。父が戦中生まれだったこともあり、私にはいとこが総勢20人以上すべてに該当することが判明したのです。しかも、4種の書類に加え、さらにもう2−3種類がいるとのこと。いとこの戸籍と、既に亡くなっている親であればその親が戸籍除票、その上の親(わたしからみて祖母)の除票まで要るという手間と書類作成の量。しかも、この件をいとこらに通知依頼した瞬間から3か月以内に手続き完了させなければ特別な理由がない限り債務が継続するという早急性もあり、泣きそうになって司法書士にすがると「しかたないですね。1件4万円でどうですか?」とのこと。もう!80万かかるくらいなら全部自分でするわい!(←今ここ)このコラムをご覧いただいている司法書士の方、これであっています?(週刊NY生活プレス2022.11から抜粋)科学的介護情報システム(LIFE)運用のポイントとアウトカム評価に向けた実践
新しい制度やシステムに慣れることは大変かもしれませんね。
今までよかれと思っていたケアがそれほど重要でなかったり、
これまで重視してなかったケアが良い影響をもたらすことがわかったり…
そんな有益な情報や新しい発見が現場にフィードバックされる。
そういったことが『科学的介護』=『LIFE』には期待されています。
いずれ日本の介護の財産になると信じて
少しずつでも取り組むことが大切なんだと思います。
-
💚💚
※ #日総研 のオンラインセミナー
「科学的介護情報システム(LIFE)運用のポイントとアウトカム評価に向けた実践」
まもなく申込締切(6/28まで)
👇
https://www.nissoken.com/s/151200/indexsf.html日本介護事情100 介護事業所の新型コロナ対策

週刊ニューヨーク生活様「日本の介護事情100」 https://www.nyseikatsu.com
祝コラム連載100回目!嬉しい話題からご提供するつもりが日本ではもう災害と言っていい、世界中にも広がりつつあるCOVID-19。いわゆる新型コロナウィルスについて日本の介護事業所対応状況について書かなくてはなりません。(お祝いコラムはまた落ち着いて)
現時点で「どうかからないか」「かかったらどうしたらいいか」ばかりが多くて、本当に介護事業所経営者の判断で大事なのは職員や利用者、もしくは自分も含めて「これってかかっているのかな。陽性?陰性?」のグレーレベルでの判断なのです。早すぎる判断に越したことがないのではなく、冷静で、隠蔽や改ざんしない健全な経営を表明することが大事です。現時点で、行政のどの通知をみても最終判断は「良きにはからえ」と逃げてる感が強く、経営側は自分の身は自分で守るが最善と思われます。
【最善を尽くすための対策】
1. 毎朝職員検温(マイ体温計)と職員互いの顔色指先確認。
2. それらの記録(利用者と同様)。
3. 対策委員会設置準備のための準備(労使関係の結束)。
4. 災害同様に備蓄や現金の最小限確保(金融や流通遮断もありえる。しかし貯め過ぎないこと)。
5. 近隣事業との連絡網の構築(モノとヒトの双方バックアップ支援準備)。
6. 事業所の保険のカバー範囲の確認。
【陽性疑いから決定までの流れ】
1. 職員が検温で37.5度以上が出たタイミングでの判断。
保健所等設置「相談・受診の目安」に準じる⇒社命で休めというか本人自主的休みかの決定。
2. 対策委員会の設置
(1)情報収集担当
(2)対行政担当(保健所、メディア)
(3)対取引先担当(他事業、利用者、ご家族)
(4)内部調整担当(職員体調、職員家族、給与保証等)
(5)委員長は上記4つをカバーと最終決定者
(委員長が罹患もあるのでバックアップ体制確保)
3. 高熱理由で複数日以上休みの場合、社命による給与保証か有給か、自主的休みかの決定。
4. 状態による陽性の疑いから保健所相談とPCR検査への検討、その上で事業所内調査。
5. 上記の3の段階で、当事業所の職員の体調の再確認。「事業の休業」か「継続」かの判断。⇒ここで判断を急ぎすぎると痒くもない風評被害つながるリスク、かといって陽性であった場合の法人対応の「後手対応」と非難されるリスクもある。
6. 管轄介護保険課へ相談。
7. 陽性?陰性?の結果が出る。
8. 陰性の場合は継続。陽性の場合、管轄保健所・介護保険課の指示に従う。同時に、対策委員会のレポートラインの再確認と事業の再開に向けての時系列計画。(消毒や近隣への説明や補償等)
と書いているうちに、3/6名古屋市が、南区と緑区の約126デイサービスに2週間休業するよう要請したとのこと。およそ5800人いる利用者に大きな影響を及ぼすことになります。このことは、全国に水道ガス電気等光熱費を遮断されるような衝撃波が広がる可能性があります。今、我々介護事業経営者は日本経済に影響させないよう防波堤を造る使命に駆られています。
当社ではあらゆる専門家と連携してコンサルティングを行っております。皆様の疑問、お悩み、日本の社会保障(介護・医療・年金・雇用等)制度に関するご質問やご相談お待ちしております。info@helpz.jp
#運営指導 #旧実地指導 #介護保険実地指導 #介護保険運営指導 #実地指導対策 #運営指導対策 #介護事業所指導監査 #介護施設監査対策 #行政指導対策 #介護保険指導監督 #デイサービス実地指導 #訪問介護実地指導 #通所介護運営指導 #通所リハ実地指導 #介護施設運営指導 #介護施設運営適正化 #介護コンプライアンス #介護法令遵守 #介護加算算定チェック #介護記録指導 #介護運営コンサルタント #介護運営コンサル #介護経営コンサルタント #介護事業経営コンサル #介護事業所コンサル #介護施設コンサルタント #デイサービス経営コンサル #訪問介護経営コンサル #介護保険施設コンサル #介護事業立て直し #介護事業所改善 #介護事業所運営改善 #介護事業所経営改善 #介護経営安定化 #介護BCP支援 #科学的介護LIFE #LIFE対応支援 #介護業務改善 #介護現場改善 #介護労務リスク #西村栄一 #ヘルプズアンドカンパニー #ヘルプズアンドカンパニー西村栄一 #実地指導レスキュー #運営適正化レスキュー #日本で唯一の介護事業所の運営適正化レスキューコンサルタント #介護運営指導の専門家 #実地指導一筋 #実地指導対策のプロ #運営指導の達人 #介護事業コンプライアンス講師 #介護経営セミナー講師 #介護保険指導監督研修講師 #実地指導準備 #実地指導シミュレーション #模擬実地指導 #運営指導事前対策 #運営指導チェック #実地指導書類整理 #介護記録整備 #個別支援計画指導 #ケアプラン点検 #加算要件確認 #返還金リスク対策 #指導監査で指摘されないために #実地指導で慌てない #訪問介護計画書指導 #デイサービス運営見直し #生活相談員体制整備 #人員基準の見直し #運営規程整備 #指導後改善フォロー #介護事業者向けコンサル #介護施設経営者向け #訪問介護事業者向け #デイサービス事業者向け #居宅サービス事業者向け #大阪介護コンサル #関西介護コンサル #全国対応介護コンサル #介護経営者のお悩み解決 #介護事業所の不安解消 #介護事業者支援 #介護事業のよろず相談 #介護経営なんでも相談 #介護事業所の駆け込み寺 #現場重視の介護コンサル #机上の空論ゼロ #介護ヘルパーは日本で一番魅力のある仕事 #企業は人なり #介護経営と現場の両立 #介護事業の持続可能性 #利用者の幸せと経営の両立 #介護業界を良くしたい #介護事業所の未来を守る
日本の介護事情99 日本の社会福祉のあり方を根底から覆すような事件の裁判

週刊ニューヨーク生活様「日本の介護事情99」 https://www.nyseikatsu.com
日本の社会福祉のあり方を根底から覆すような事件の裁判の「死刑求刑」がありました。
神奈川県立の知的障害者施設で元施設職員の男が、入所者19人を刺殺、いわゆる「相模原障害者施設殺傷事件」です。求刑内容は「単独犯としては類を見ない。計画的で残虐、生命軽視が顕著。正当性を主張し続け、更生の意欲も可能性もない」と死刑求刑。これだけ一方的に殺して、当然すぎるといえば当然だという声が多いのですが、私は、その動機に少し違和感を覚えました。犯人の言葉に「意思疎通のできない人間は生きる価値がない」「生産能力のない者を支える余裕はこの国にはない」と言う合理主義・非生産性の排除の風潮は、これからの日本の行先方向性が一致しているのではないかと言う不安です。このコラムの連載でも労働力の不足を解決するには「生産性を上げなければならない」とか「時間当たり採算(RPA)が必要だ」と明示してきました。その私への警鐘でもあります。この事件で向き合わなければならないのは、極端な「生産性」を巡る問いについてです。だからと言って、その背景をもって犯人の殺人行為を肯定するべきではないし、議論の余地すらないとも言えるでしょう。しかし、現代を生きる私たちは多かれ少なかれ、「生産性」で「自分の価値」を測られる焦りと恐怖の時代の「圧力」にさらされているのは確かなのです。その圧力に負けないための方法を6つ提案します。
① 多様な人同士が「共に」生きることを自覚し、他人にも広げていくこと。
福祉の世界で働いている人間は、他の業界で働いている人よりもその肌感覚はあるはずと思われていますが、そう言う当たり前の環境の中で働いていると、だんだん麻痺してしまい、ただの「重度障害者」と括ってしまう慣れが出てくる人もいます。「人」として見えにくくなってしまうこともあるのかもしれません。障害者や要介護者は「役に立たない」「してやっている」という決めつけに対して、「こんな風に生きているよ、暮らしていけるよ」ということを身近に示し、広げていくことが最初の一歩なのかもしれません。そしてそのために、本人の意思を知ろうとし、意思に基づく行動を支援するという姿勢が大切です。
② 「生きる」と「生産性」を混同して議論しないこと。
私たちは知らず知らずのうちに、「内なる優生思想」が存在します。無意識の中で生まれる得体の知れない何かがあります。「自分と違う、なんだか遠い」と感じられる存在に対しては、つい表面的な印象で決めつけてしまいがちです。ただし、「優生思想」はつい最近のものであり、さらに「生産性の向上」へ傾倒していくことでさえこれからの施策です。日本は1400年以上も前、聖徳太子は、大阪の四天王寺に「悲田院」と呼ばれる施設を作り、戦で親を亡くしたり、病気で子供を失ったり、身寄りの無い人たちの為に、無償で介護をする優しい文化や思想がDNAに刻まれています。
その他、③定期研修で理念や行動指針の浸透。④腰痛予防やメンタルヘルスケアへの取り組み。⑤朝礼(申送り)と会議の見直し。⑥定時退社や休暇取得しやすい職場作り。
決して遠い異国の事件ではない、気がつけば隣にいるような悲惨な事件。自分の考え方の整理、他人へによって、また、これからの日本が間違った方向にいかないために、私の身近なところ(顧問先の施設)から浸透していけるように徹底します。
当社ではあらゆる専門家と連携してコンサルティングを行っております。皆様の疑問、お悩み、日本の社会保障(介護・医療・年金・雇用等)制度に関するご質問やご相談お待ちしております。info@helpz.jp
#運営指導 #旧実地指導 #介護保険実地指導 #介護保険運営指導 #実地指導対策 #運営指導対策 #介護事業所指導監査 #介護施設監査対策 #行政指導対策 #介護保険指導監督 #デイサービス実地指導 #訪問介護実地指導 #通所介護運営指導 #通所リハ実地指導 #介護施設運営指導 #介護施設運営適正化 #介護コンプライアンス #介護法令遵守 #介護加算算定チェック #介護記録指導 #介護運営コンサルタント #介護運営コンサル #介護経営コンサルタント #介護事業経営コンサル #介護事業所コンサル #介護施設コンサルタント #デイサービス経営コンサル #訪問介護経営コンサル #介護保険施設コンサル #介護事業立て直し #介護事業所改善 #介護事業所運営改善 #介護事業所経営改善 #介護経営安定化 #介護BCP支援 #科学的介護LIFE #LIFE対応支援 #介護業務改善 #介護現場改善 #介護労務リスク #西村栄一 #ヘルプズアンドカンパニー #ヘルプズアンドカンパニー西村栄一 #実地指導レスキュー #運営適正化レスキュー #日本で唯一の介護事業所の運営適正化レスキューコンサルタント #介護運営指導の専門家 #実地指導一筋 #実地指導対策のプロ #運営指導の達人 #介護事業コンプライアンス講師 #介護経営セミナー講師 #介護保険指導監督研修講師 #実地指導準備 #実地指導シミュレーション #模擬実地指導 #運営指導事前対策 #運営指導チェック #実地指導書類整理 #介護記録整備 #個別支援計画指導 #ケアプラン点検 #加算要件確認 #返還金リスク対策 #指導監査で指摘されないために #実地指導で慌てない #訪問介護計画書指導 #デイサービス運営見直し #生活相談員体制整備 #人員基準の見直し #運営規程整備 #指導後改善フォロー #介護事業者向けコンサル #介護施設経営者向け #訪問介護事業者向け #デイサービス事業者向け #居宅サービス事業者向け #大阪介護コンサル #関西介護コンサル #全国対応介護コンサル #介護経営者のお悩み解決 #介護事業所の不安解消 #介護事業者支援 #介護事業のよろず相談 #介護経営なんでも相談 #介護事業所の駆け込み寺 #現場重視の介護コンサル #机上の空論ゼロ #介護ヘルパーは日本で一番魅力のある仕事 #企業は人なり #介護経営と現場の両立 #介護事業の持続可能性 #利用者の幸せと経営の両立 #介護業界を良くしたい #介護事業所の未来を守る
-
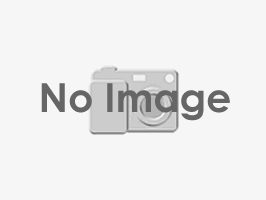 科学的介護情報システム(LIFE)運用のポイントとアウトカム評価に向けた実践
新しい制度やシステムに慣れることは大変かもしれませんね。今までよかれと思っていたケアがそれほど重要でなかったり
科学的介護情報システム(LIFE)運用のポイントとアウトカム評価に向けた実践
新しい制度やシステムに慣れることは大変かもしれませんね。今までよかれと思っていたケアがそれほど重要でなかったり
-
 気が遠くなりそうな相続放棄の苦労話
要介護1の父の軽い介護から一転、その後の死後整理の段階に入って早1か月。日本の介護事情を私自身が肌身に染みてい
気が遠くなりそうな相続放棄の苦労話
要介護1の父の軽い介護から一転、その後の死後整理の段階に入って早1か月。日本の介護事情を私自身が肌身に染みてい
-
 介護施設と縁のある有名人やアスリート
お久しぶりに歓喜の声をあげることがありました。日本サッカーが強豪国ドイツに勝ったのです。この勝利景気がもたらし
介護施設と縁のある有名人やアスリート
お久しぶりに歓喜の声をあげることがありました。日本サッカーが強豪国ドイツに勝ったのです。この勝利景気がもたらし
-
 実名報道に思うこと「社会的制裁」優先に疑問
ハッピー!な話題に持って行きたいのですが、私の気持ちが今整っていないんですかね。なんとなくネガティブなニュース
実名報道に思うこと「社会的制裁」優先に疑問
ハッピー!な話題に持って行きたいのですが、私の気持ちが今整っていないんですかね。なんとなくネガティブなニュース
-
 介護の敷居が高くなる?
2023年の日本の介護は翌年2024年の介護・診療・障害者の制度と報酬の同時改定の議論が丸一年かけて年末までに
介護の敷居が高くなる?
2023年の日本の介護は翌年2024年の介護・診療・障害者の制度と報酬の同時改定の議論が丸一年かけて年末までに